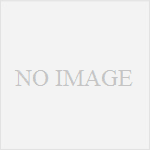こんばんは。TAK666です。
レジデントが代わる代わるオススメハードテクノを紹介するこのコーナー、
2週間ぶりにワタクシが担当致します。
Hardonize10周年もいよいよ2日後に迫ってまいりました。
再三の掲載になりますが、概要はこちらでございます。
一口にハードテクノと言っても明暗緩急様々なスタイルがある音楽でございますので、我々レジデントも10年分の歩みを体現するつもりで皆様のお越しをお待ちしております。
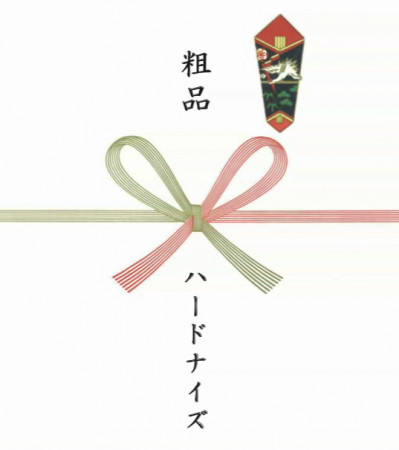
ちなみに先週からこんな画像が公開となっておりますが、10周年の感謝を込めてささやかながら来場された方へのプレゼントをご用意しております。
大凡見当は付くかと思いますが、何であるかはお楽しみに。
それに因んで過去2回のワタクシ担当回では10年前のテクノ、ハードテクノシーンについて触れました。
時代を感じる点もあれば今に通ずるところもあったり、10年前の時点でも楽曲のカラーは様々でした。
いつの時代も物好きによって支えられている音楽だなと思いますね。
ところで、物好きと云えば日本のとある界隈にスポットを当てて語ることもできるのではないでしょうか。
ここに2冊のカタログがあります。

当連載でも度々取り上げている同人音楽、日本のインディーズ音楽の即売会、M3の2008年のものです。
ちなみにウチには自分が当即売会に行き始めた2003年から現存してます。
この時まだ会場が蒲田の会場で、出店者数も今と比べれば全然小規模なものでした。
実数を挙げると、
| 時期 | 参加サークル数 |
|---|---|
| 2008年春 | 420 |
| 2008年秋 | 455 |
に対して
| 時期 | 参加サークル数 |
|---|---|
| 2016年秋 | 1334 |
| 2017年春 | 1381 |
と、4倍になっております。(M3公式サイト調べ。)
この中に各アレンジやバンドサウンド、ボイスラジオなどが含まれるため、当然クラブミュージックに絞るともっと少なくなるワケです。
出展サークルは参加時に自分がリリースする作品のジャンルをタグとして登録できるのですが、主なクラブミュージックのジャンルに対する参加サークル数を2008年春と2017年秋で比較すると
| ジャンル | 2008年春 | 2017年秋 |
|---|---|---|
| テクノ | 32 | 42 |
| トランス | 21 | 36 |
| ハウス | 5 | 30 |
| ドラムンベース | 6 | 27 |
| ハードコア | 11 | 63 |
こんな感じ。(※)
ハウスとハードコアの伸び率が凄いですね。
クラブミュージックの世界で見た流行はここ同人音楽にも確実に届いている感じがします。
従って昨年秋に行われたM3でリリースされた作品のレビューなどを巨大な圧力によってやらされたりもしましたが、ここで取り上げたサークルも当時はほぼ存在しなかった、そんな時代です。
※
タグは複数登録できる以上、各ジャンル間でのサークルの重複はあるのでこの合計がクラブミュージック総数とはいきません。
あとテクノはテクノポップとかエレクトロニカなどの非ダンスミュージックも結構含まれます。
では当時クラブミュージックの文脈で作品をリリースしていたサークルはどんなものがあっただろうか?と云うのが今回のテーマになります。
個人的な縁としてはハードコアの方が書きやすかったりはするのですが、Hardonizeレジデントの立場から主にテクノへ焦点を当てます。
また、折角手元にカタログがあるので、これから取り上げるのも2008年にM3へ参加していたサークルに絞りたいと思います。
題して10年前の同人テクノ事情、いってみましょう。
まずはこちら。
現在は秋葉原重工にも名を連ねているFumiaki Kobayashi氏が2007年から運営しているサークル。
元よりソロ、ユニットで様々なレーベルからテクノをリリースしていた経験を生かし、レーベル設立と同時にPresenceと云うEPシリーズを始めます。
参加メンバーはFumiaki Kobayashi氏の他はR-9氏、Ryo Ohnuki氏、Atsushi Ohara氏で完全に固定。
また、データ領域に各トラックのMP3や、サンプリング素材が入っていたりと今でも珍しいと思える試みを行っていました。
サウンドは後の秋葉原重工に繋がる肉厚なハードミニマル。
同人音楽のフィールドでこの手の音をリリースしていたサークルは数えるくらいしかないように思います。
同時期のハードテクノサークルで思いつくのはAtsushi Ohara氏が設立したLINEARや、Alstroemeria RecordsのMasayoshi Minoshima氏がサイドプロジェクトとして展開していたDown Force Records、少し後にはクラブフィールドで活動していたGo Hiyama氏、Takaaki Itoh氏を擁するAsianDynastyがM3に殴り込みをかけるなんて出来事もありましたが、現在進行形で活動しているサークルを除けば本当にそれくらいです。
尚、Bandcampの試聴埋め込みがあるようにこのサークルの作品は現在でも買えるんです。
Presenceシリーズ10作品全部買っても2000円そこらなので、当時を知る切欠、或いはハードテクノを知る切欠として是非。
bandcamp – gatearray recordings
1990年代と云えば初頭に電気グルーヴが結成され、徐々にKen Ishiiや田中フミヤの存在が知れるようになり、攻殻機動隊やWIPEOUTと云ったゲームとテクノの融合と云った出来事など挙がるトピックにキリがありませんが、そのジャパニーズテクノの系譜をモロに辿ったようなサークルが存在します。
それがこのLOOPCUBE。
石野卓球から古代祐三まで幅広くVJをこなしてきたH/de.氏と今尚自身のサークルluvtraxで活動をしているquad氏をコアメンバーとして2000年に発足された老舗サークルです。
前述の通り、両者共90年代からテクノをリアルタイムで聴いてこられた経歴の持ち主であり、数々のクラブパーティーにも出演経験のある方々。
そのバックグラウンドが遺憾なくこのLOOPCUBEで発揮されておりますが、後に月は東に日は西に~Operation Sanctuary~や後にびんちょうタンなどアニメ、ゲームサウンドも広く手掛けるようになるなど、一口に語り尽くせない活動を展開しました。
このfragranceと云う作品は10年前である2008年に出た作品で、アシッドあり、テクノポップあり、チップチューンあり、また、当時発売したてのボーカロイドを採用すると云う挑戦的な面もありながら主軸はテクノと云う完成度の高い逸品。
最後に虹のアレンジを差し込んでくる辺りニヤリとさせられます。
ちなみに発起人のH/de.氏によってLOOPCUBEの歩みがまとめられたページがございます。
これも大変貴重な資料だと思うので是非ご覧ください。
LOOPCUBE年表
2011年に物心ついた歳を迎えていた人であればこの元ネタに心当たりが大いにあるでしょうし、何ならこのアレンジも耳にしたことがある筈です。
自身を1号店ジャーナリスト、麻婆ドーファーと評し、それぞれブログで連載を繰り広げ、何なら本(※)も出版している異色音楽家、BUBBLE-B氏が自身のレーベルとしていたのがこちら。
※Amazon – BUBBLE-B (著) – 全国飲食チェーン本店巡礼 ~ルーツをめぐる旅~
初作は1994年、しかも媒体はカセットテープでのリリースと云った辺り、更に歴史を感じさせます。
当初から同人サークルとして活動していたワケではなく、インディーズ系CDショップや書簡での直接やり取りによって頒布していたと云うから現物を持っている人は相当少数だと思われます。
冒頭に取り上げたようにBUBBLE-B氏の音楽は何かしら日本語のネタモノを用いたテクノ、所謂ナードコアと呼ばれるもので、同時期に活動していたアーティストとしてはLeopaldonやサイケアウツ、サークルで言えばFoxyun氏によるXROGERやDieTRAX氏による全日本レコードなどが挙げられます。
完全に余談ですが、Hardonizeの翌日、こんなパーティーが執り行われるそうなのでご興味のある方は是非足を運んでみてください。
TwiPla – ゆめかわナードコアまつり(仮)
さて、BUBBLE-B氏はソロの他にもテクノユニットを結成しておりますが、これも映像を見て貰った方が早い。
http://nkzm07.wixsite.com/karatechno
これを何と評したら良いのでしょう。
真面目に理解しようとすると頭がパンクして死ぬタイプに属します。
公式サイトでは
“カラテクノは、ハードコア・テクノとフルコンタクト空手の融合を試みる、唯一無二の演武レイヴ・パフォーマンス・ユニットです。”
この通り謳っており、これ以上説明する術を持ち合わせておりません。
しかしトラックはメチャクチャカッコ良いです。
この通りBandcampで配信中ですので購入が可能。
古今東西2度と現れないユニットだと思うので死ぬ前に是非。
音を取り込むサンプラー、ビートを鳴らすリズムマシン、そしてその2つを集約させるシーケンサーと云えばヒップホップに於ける3種の神器のようなものですが、これをアニメサンプリングに転用させ、同人音楽の中でも更に土臭いダンスミュージックを手掛けていたサークルがありました。
それがEx-man氏、DJ Wagonsale氏によるA.G.経営デッドロッカーズ。
Trax Recordsに良く似たロゴから汲み取れる通り、シカゴハウス的なゲットー感が漂う作品が肝。
Tokyo Electro Beat Parkや本間本願寺氏のビッグファイアが来るまではこの手のジャンルすら同人音楽にはなかったように思います。
調べて分かったのですが、過去に茶箱に縁のある方々で行われていたアニソンパーティー、SS|EX NITEへゲストとして出演経験もあったことが判明。
現在はサークルとしての活動は行っていない模様ですが、メンバーのEx-man氏は変名義で曲を作り続けている様子。
こちらもオールドスクールライクなテクノが揃ってます。
https://soundcloud.com/nase-from-azumanase
https://nase1973.bandcamp.com/
もっとストイックに1つ1つの音の作り込みに魂を削っていたサークルもありました。
Czk氏とgray氏によって2008年に結成されたDisorder Circulationはプログレッシヴ、テクノ、アンビエント、IDMなど様々な要素が入り混じった独自の世界観を形成していました。
エレクトロニカ的アプローチが入ると非クラブミュージックとして先入観を持たれがちですが、2人組ユニットとしてパーティーでのDJ、ライブ経験があることもあり、実際聴いてみるとかなりフロアユースだったりします。
アンダーグラウンドの実力者と云うか、シンプルなジャケットのデザインからもその辺りが伝わってきます。
こちらもBandcampで初期作品から配信しているので、上の埋め込みからどうぞ。
同時期に活動していた同系統のサークルとしては濃密で重厚なサウンドにアニメネタのリリックが乗った異形ヒップホップを作っているくっつり会、繊細な音使いと狂気的なサンプリングの合間を縫うドラムンベース、エレクトロニカが特徴のKPDrecords、2002年から長年に渡って生音、電子音入り混じったノイジーなインダストリアルミュージックを提示し続けているCyber Logic Pro.などが挙げられます。
この界隈の作品はそれぞれ何かしらのこだわりが強く、それユエの斬新なアイディアみたいなものが垣間見えて大変同人音楽らしいと思うわけです。
さて、まだまだ取り上げたいサークルはいっぱいあるのですが、最後に1つだけどうしても紹介したいものがございます。
上でもちらほら出ておりましたが、この時代になるとM3やコミックマーケットで作品をリリースしつつ、クラブパーティーにも出演していると云った方が珍しくなくなってきました。
中にはあまつさえオーガナイズ側に回る人もおりまして、今回お招きしたYamajet氏はまさにそんな人です。
彼が2008年から始めたパーティーはパーティーでありながら音楽以外の部分に主眼を据え、しかし自由度に富んだ多様な音楽が聴けるものとして今尚印象に残っているものでした。
その名も『ビア充』。
『ビールが美味しい』を合言葉に初回は茶箱で開催され、その後バーに場所を移し、挙句大阪やMOGRAに進出したと云う変遷も凄まじいですが、毎回消費されるビールの量もまた凄まじく、この界隈に於ける元祖酒飲みパーティーとして深く印象に残っております。
私は666に因んで6回目に出演させて頂きました。
で、そのビア充には初回からパーティーアンセムが存在しまして、それを作ったYamajet氏はこの曲からプレイスタートか、パーティーの〆に流すか、或いはその両方がお決まりのパターン。
つまり今年はこの曲から10年にも当たるわけです。
めでたい気持ちと共にご紹介致します。
日本でも毎年行われているドイツのビール祭『オクトーバーフェスト』で乾杯時に流れる宴会ソングが元ネタ。
今やすっかりビールの人として定着してしまっているYamajet氏ですが、それを語るにはやはりこの曲があってこそだと私は思ってしまいますね。
ちなみにこちらからダウンロードが可能。
V.A. – Ein Prosit ep.
以上、2008年の同人テクノを振り返る回でした。
前々回、前回と10年前のテクノにスポットを当ててお送りしてきましたが、裏テーマとして今回のHardonizeにお招きした3名それぞれのバックグラウンドにスポットを当てておりました。
日本に於けるテクノ黎明期より国内シーンを支え、block.fmでパーソナリティーを務めるなど、日本から世界に発信し続けているTAKAMI氏。
海外レーベルに見出され、欧州ツアーやリリースを重ねて逆輸入的に日本で知る人ぞ知る存在となっている本間本願寺氏。
そしてクラブミュージック外と思われていた同人音楽と云う場所からクラブ、パーティーに深く関わってきたYamajet氏。
それぞれバックグラウンドは異なれど、それぞれの解釈の元にハードテクノを表す、そんなひと時になるでしょう。
ゲストVJとしてお招きしたcoda氏も去年ワタクシの30歳記念パーティーでアホな曲にアホな映像で応えて貰うなどバッチリカマして貰ったこともあり、大変信頼を寄せております。
パーティー前としてはこれが最後の連載記事となりますので、あとは皆様、現場でお会い致しましょう。
よろしくお願い致します。
次週02月13日は774Muzikさんが担当します。今回はこれにて。